コロニーと呼ばれる集団をつくり階層社会を営む「真社会性生物」の驚きの生態を、進化生物 学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく語った名著『働かないアリに意義がある』がヤマケイ文庫で復刊! 働かないアリが存在するのはなぜなのか? ムシの社会で行われる協力 、裏切り、出し抜き、悲喜こもごも――面白く、味わい深い「ムシの生きざま」を紹介する。
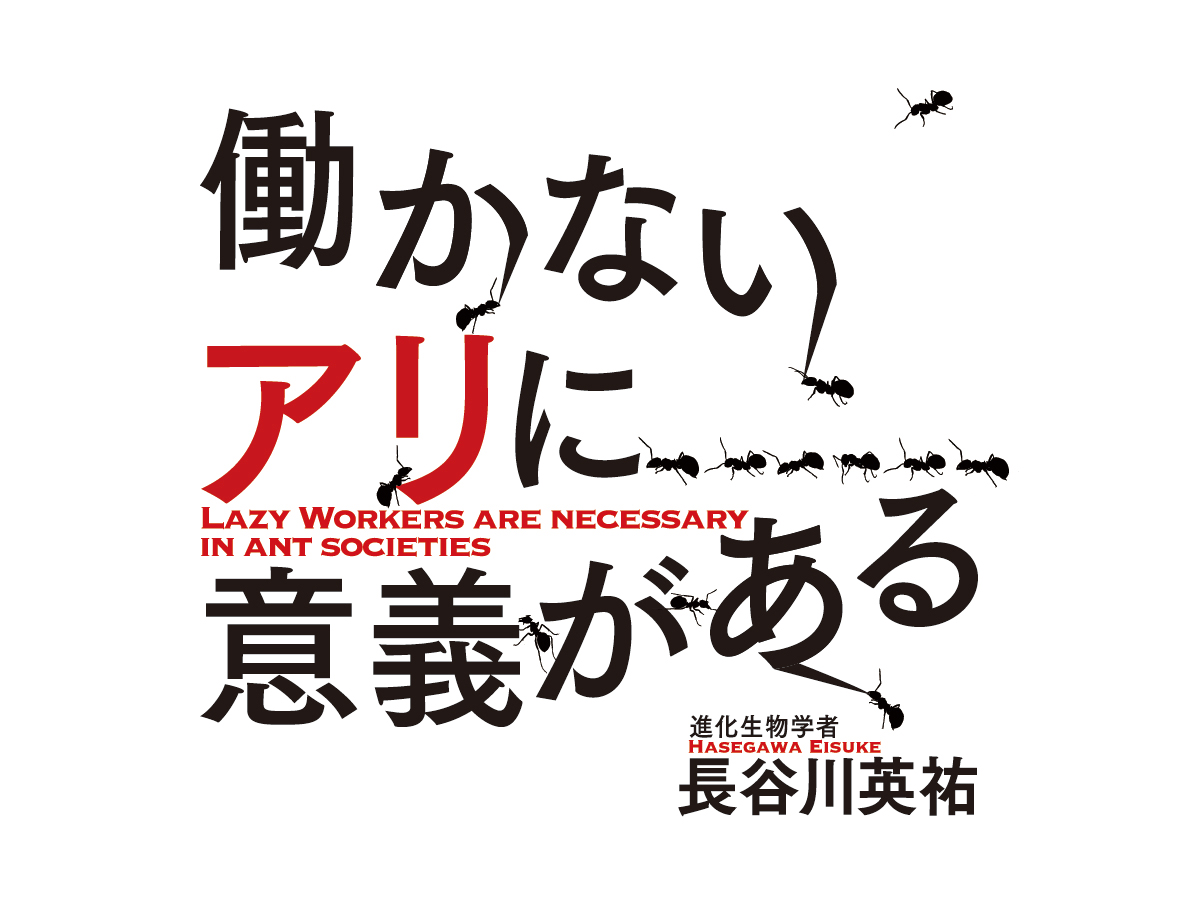
よく働くアリ、働かないアリ
かなり単純な判断しかできないハチやアリたちのコロニーが効率よく仕事を処理していくためには、必要な個体数を必要な場所に配置するメカニズムが必要です。人間の会社では、これは上司の仕事です。
しかし昆虫社会に上司はいないので、別のやり方が必要になります。このために用意されているのが「反応閾値(いきち) 」=「仕事に対する腰の軽さの個体差」です。
「反応閾値」とは耳慣れない言葉ですが、社会性昆虫が集団行動を制御する仕組みを理解するためには欠かせない概念ですので、できるだけわかりやすく説明します。
例えば、ミツバチは口に触れた液体にショ糖が含まれていると舌を伸ばしてそれを吸おうとしますが、どの程度の濃度の糖が含まれていると反応が始まるかは、個体によって決まっています。この、刺激に対して行動を起こすのに必要な刺激量の限界値を「反応閾値」といいます。
わかりやすく人間にたとえてみましょう。人間にはきれい好きな人とそうでもない人がいて、部屋がどのくらい散らかると掃除を始めるかが個人によって違っています。
きれい好きな人は「汚れ」に対する反応閾値が低く、散らかっていても平気な人は反応閾値が高いということができます。要するに「個性」と言い換えることもできるでしょう。
ミツバチでは、蜜にどの程度の濃度の糖が溶けていればそれを吸うか、とか、巣の中がどれくらいの温度になると温度をさげるための羽ばたきを開始するかというような、仕事に対する反応閾値がワーカーごとに違っている、ということが昔からわかっていました。
つまり、必要とされる行動に対する反応しやすさに個体差があるのです。
人間なら何人かの人がいれば、かならずきれい好きとそうでもない人が交じっており、きれい好きな人は少し散らかると我慢ができず掃除を始めてしまいます。仕事に対する「腰の軽さ」が違っているから、すぐやる人とやらない人がいるというわけです。
ミツバチに話を戻すと、ワーカーのあいだに個性が存在することがわかったので、それがなんのために存在するかについて学者たちは知恵を巡らせ、一つの仮説にたどり着きました。それは「反応閾値モデル」と呼ばれるものでした。
これは、反応閾値がコロニーの各メンバーで異なっていると、必要なときに必要な量のワーカーを動員することが可能になるとする考え方です。
コロニーが必要とする労働の質と量は時間と共に変わります。どれだけの働きバチを蜜源に向かわせなければならないかは、どれだけの花が発見されたかによって変わります。幼虫がたくさんいて、みなが腹を空かせている時間にはたくさんの働きバチが幼虫にエサを与える必要がありますが、幼虫が満腹している時間にはそれほどたくさんのハチが働く必要はありません。
こなさなければならない仕事の質と量にこのような時間的・空間的な変動があるとき、それに効率よく対処するにはどうしたらよいでしょう。
人間なら、仕事の発生状況をマネージャーなどが把握して、人をそれぞれの現場に振り分ける、という対処をするでしょう。外回りの最中、会社から指示を受けて別の現場に急行、という経験をおもちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ハチやアリではそのような対応は不可能です。昆虫の単純な脳では、人が極度に発達させた大脳の前頭葉で処理しているような、高度な知能的判断をくだすことはとてもできません。そこで真社会性生物ができることのなかから選んだ方法(厳密にいえば自然淘汰の結果、残された行動様式ですが)は、メンバーのなかに労働に対する反応閾値の幅をもたせるというものでした。
反応閾値に個体差があると、一部の個体は小さな刺激でもすぐに仕事に取りかかります。例えば、敏感な個体は幼虫が少し空腹になった様子を察知して、すぐにエサを与えます。幼虫たちはたくさんいるので、他の幼虫も空腹になった場合、敏感なハチたちが懸命に働いても手が足りなくなるでしょう。
一部の幼虫はさらに空腹になり、早くエサをくれ!とむずかりだします。つまり、幼虫の出す「エサをくれ」という刺激はだんだん大きくなっていきます。すると、いままで幼虫に見向きもしなかったハチたちのうち、それほど敏感ではない働きバチも幼虫にエサを与え始めます。
それでも手が足りなければ幼虫の出す刺激はさらに大きくなり、最も鈍感なハチたちまでエサやりを始めます。幼虫が満腹になってくると敏感なハチだけでも手が足りるようになるため、鈍感なハチから順に仕事をやめてだんだんと働き手は減っていきます。
やがて全部の幼虫が満腹すると、「エサをくれ」という刺激はなくなり、どのハチも幼虫にエサを与えなくなります。
このように、反応閾値に個体差があると、必要な仕事に必要な数のワーカーを臨機応変に動員することができるのです。このメリットが、司令官をもつことができない社会性昆虫たちのコロニーに個性が存在する理由ではないかとする仮説が「反応閾値モデル」です。
怠け者は仕事の量で変身する
また、ある個体が一つの仕事を処理していて手いっぱいなときに、他の仕事が生じた際、その個体が新たな仕事を処理することはできませんが、新たな仕事のもたらす刺激値が大きくなれば反応閾値のより大きな別の個体、つまり先の個体より「怠け者」の個体がその仕事に着手します。
このシステムであれば、必要な個体数を仕事量に応じて動員できるだけでなく、同時に生じる複数の仕事にも即座に対応できます。しかも、それぞれの個体は上司から指令を受ける必要はなく、目の前にある、自分の反応閾値より大きな刺激値を出す仕事だけを処理していれば、コロニーが必要とする全部の仕事処理が自動的に進んでいきます。
高度な知能をもたない昆虫たちでも、刺激に応じた単純な反応がプログラムされていれば、コロニー全体としてはまるで司令官がいるかのように複雑で高度な処理が可能になるわけです。
つまり、腰が軽いものから重いものまでまんべんなくおり、しかしさぼろうと思っているものはいない、という状態になっていれば、司令塔なきコロニーでも必要な労働力を必要な場所に配置できるし、いくつもの仕事が同時に生じてもそれに対処できるのです。
よくできていると思いませんか? 面白いのは、「全員の腰が軽かったらダメ」というところで、様々な個体が交じり合っていて、はじめてうまくいく点がキモです。
ミツバチの例から、このような反応閾値の個体間変異が実際に存在していることはわかっています。人間から見るとみんな同じに見えるハチやアリたちは、実はそれぞれ違う個性をもっているのです。
※本記事は『働かないアリに意義がある』を一部掲載したものです。
『働かないアリに意義がある』
今の時代に1番読みたい科学書! 復刊文庫化。アリの驚くべき生態を、進化生物学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく、深く、面白く語る。
『働かないアリに意義がある』
著: 長谷川 英祐
発売日:2021年8月30日
価格:935円(税込)
【著者略歴】
長谷川 英祐(はせがわ・えいすけ)
進化生物学者。北海道大学大学院農学研究員准教授。動物生態学研究室所属。1961年生まれ。
大学時代から社会性昆虫を研究。卒業後、民間企業に5年間勤務したのち、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。
主な研究分野は社会性の進化や、集団を作る動物の行動など。
特に、働かないハタラキアリの研究は大きく注目を集めている。
『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書)は20万部超のベストセラーとなった。
からの記事と詳細 ( 「上司がいなくても仕事がまわる」優れた組織が持つ「ある特徴」――アリが教えてくれること - 株式会社 山と溪谷社 )
https://ift.tt/2XLCTAS
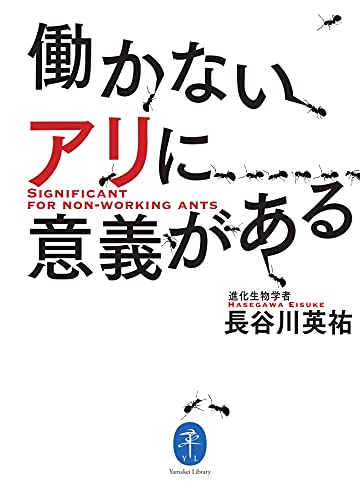
No comments:
Post a Comment